Ғ@•cӮрҗAӮҰӮЬӮөӮҪҒB
ғNғҢғ}ғ`ғX(Ӯ«ӮсӮЫӮӨӮ°үИ) |
|
 |
Ғ@
Ғ@Ҹ¬’№ӮҪӮҝӮ©ӮзӮМ‘ЎӮи•ЁӮЕӮ·ҒBҚЕҸүӮЙҠҰ’ЦӮМүәӮ©ӮзүиӮӘҸoӮД—ҲӮДӮ©Ӯз4”N–ЪӮЙӮөӮДӮжӮӨӮвӮӯүФӮрҚзӮ©Ӯ№ӮйӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮЬӮөӮҪҒBҢіӮМҸкҸҠӮЕӮНүиӮрҸoӮ·ӮҪӮСӮЙҗA–Шү®ӮіӮсӮЙҗШӮзӮкӮДӮөӮЬӮӨӮМӮЕҒAҗШӮзӮкӮИӮў—lӮЙ•ЁүAӮЕҒA– ӮӘү„ӮСӮкӮО“ъ“–ӮҪӮиӮМ—ЗӮўҸкҸҠҒcӮЖҺvӮБӮД•ЁҠұӮө‘дӮМүAӮЙҲЪҗAӮөӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAҚЎҚlӮҰӮйӮЖӮИӮсӮЖӮа–іҗҲӮИҸкҸҠӮҫӮБӮҪӮЖ”ҪҸИӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB
Ғ@ғeғbғZғ“ӮЖғNғҢғ}ғ`ғXӮН—eҲХӮЙӢж•КӮӘӮВӮ«ӮЬӮ№ӮсӮӘҒA—ј•ыӮЖӮа“ъ–{ҢҙҺYӮЕ•ПҲЩӮөӮвӮ·ӮҪӮЯӮЙ‘Ҫ—lҗ«ӮӘҚӮӮўғJғUғOғӢғ}ӮрҢіӮЙҚмӮзӮкӮҪүҖҢ|•iҺнӮҫӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒBҢsӮӘ“SӮМҗьӮМ—lӮЙӢӯӮўӮұӮЖӮ©ӮзӮұӮМ–јӮӘӮВӮўӮҪӮЖҢҫӮӨ“SҗьӮНҒAҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙ“ъ–{ӮЕүь—ЗӮіӮкӮҪӮаӮМҒBғNғҢғ}ғ`ғXӮН19җўӢIӮЙғҲҒ[ғҚғbғpӮЙҺыҸWүЖӮЙӮжӮБӮДӮаӮҪӮзӮіӮкӮҪғJғUғOғӢғ}ӮӘ•iҺнүь—ЗӮіӮкӮҪҢгӮЙӢt—A“ьӮіӮкӮҪ•ЁӮМӮжӮӨӮЕӮ·ҒB |
 |
Ғ@ғEғ“ғiғ“ғGғ“ғVғXҒ@
Ғ@2010”Nҗ¬“cҺRӮЦҸүҢwӮЙҚsӮБӮҪҚЫӮЙҒAҺQ“№ӮМӮЁ“XӮЕ”ғӮБӮҪ“~ҚзӮ«ӮМғNғҢғ}ғ`ғXӮЕӮ·ҒB“~ҚзӮ«ӮН’ҝӮөӮўҸгӮЙҒAҸ¬ӮіӮИ”’ӮўғxғӢҢ^ӮМүФӮӘүВҲӨӮ©ӮБӮҪӮМӮӘҒAҠбӮрҺдӮ«ӮЬӮөӮҪҒB
Ғ@Ҹ¬ӮіӮИғ|ғbғg•cӮҫӮБӮҪӮМӮЕҒAҚзӮӯӮМӮНүҪ”NӮ©җжӮҫӮлӮӨӮЖ2011”N“~ӮНNo CheckӮЕӮөӮҪҒBӮӘҒAӢvӮөӮФӮиӮЙ’лӮЙҸoӮДӮЭӮҪӮзҒAҢ©ӮҰӮИӮў— ‘ӨӮМ•ыӮЕӮРӮБӮ»ӮиӮЖ2—ЦүФӮӘҚзӮўӮДӮўӮйӮМӮрӮЭӮВӮҜӮЬӮөӮҪҒBӮўӮВӮ©ӮзҒAӮЗӮсӮИеQӮр•tӮҜӮДӮўӮҪӮМӮ©ҒHӮўӮВҚзӮӯӮ©ҒHӮЖ‘ТӮВӮМӮаҠyӮөӮЭӮҫӮБӮҪӮМӮЙҒAӮҝӮеӮБӮЖҺc”OҒB—Ҳ”NӮНӮұӮЬӮЯӮЙCheckӮөӮҪӮўӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB |
 |
ғNғҢғ}ғ`ғXҒEғyғgғҠғG
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ҒiғLғ“ғ|ғEғQүИҒj
Ғ@”–—ОҗFӮМүФӮӘ’ҝӮөӮӯӮД2011”NӮЙ”ғӮўӮЬӮөӮҪҒB2012”NҸtҒAӮ ӮЬӮи– ӮӘҗLӮСӮёҒAӮаӮӨ‘К–ЪӮ©ӮИҒHӮЖҺvӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAҸӯӮөӮОӮ©ӮиүФӮрӮВӮҜҒAҸtӮрҚҗӮ°ӮДӮӯӮкӮЬӮөӮҪҒBғlғbғgӮЕ’ІӮЧӮҪӮзҒAҗ¬’·ӮӘ’xӮӯ1”N‘OӮЙҗLӮСӮҪҢГӮўҺ}ӮЙүФӮр•tӮҜӮйӮМӮҫӮ»ӮӨӮЕҒAҢГӮӯӮИӮБӮҪӮ©ӮзӮБӮДҗШӮБӮДӮөӮЬӮБӮДӮНӮўӮҜӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB
Ғ@2013”NҸtӮНҒAҢ©Һ–ӮИҚзӮ«ӮБӮХӮиҒAҚw“ьӮөӮД—ҲӮҪҺһӮМ—lӮЕҒAҢҫӮӨҺ–ӮИӮөҒIӮВӮйӮрҗШӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮӘҗіүрӮЕӮөӮҪҒR(^ҒB^)ғm |
ғҶғҠүИӮМ’ҮҠФ
Ғ@ӮЦғҒғҚғJғҠғX
Ғ@ӮP“ъүФӮЕ—[•ыӮЙӮНӮөӮЪӮсӮЕӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒBӮЬӮҪҺ„ӮЙӮЖӮБӮДӮНғAғҒғҠғJ“ҢҠCҠЭӮМҚӮ‘¬“№ҳHӮМҗAӮҰҚһӮЭӮЙӮҪӮӯӮіӮсҗAӮҰӮзӮкӮДӮўӮҪҺvӮўҸoӮМүФӮЕӮаӮ ӮиӮЬӮ·ҒBҗAӮҰӮБ•ъӮөӮЕӮа–Ҳ”N‘қӮҰӮДҢ©Һ–ӮЙүФӮрҚзӮ©Ӯ№ӮйӮ©ӮзӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB
Ғ@ҺКҗ^’ҶүӣӮМүФӮНҸ¬гNҢ№‘ҫҳYүж”ҢӮМӮЁ’лӮЙӮ ӮБӮҪҠ”ӮМ‘·Ҡ”ӮЕӮ·ҒBҚЕҸүӮН–ј‘OӮӘ•ӘӮ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕҒuҸ¬гNӮіӮсӮМүФҒvӮЖҸҹҺиӮИ–јӮЕҢДӮсӮЕӮўӮЬӮөӮҪҒB
Ғ@ҺКҗ^үEӮМүФӮНҒAҸ¬ӮФӮиӮЕү©җFӮўӮМӮЕҒA“ҜӮ¶Һн—ЮӮМҳaҺнҒEғjғbғRғEғLғXғQӮрҳA‘zӮіӮ№ӮЬӮ·ҒB |
 |
 |
|

ғhғCғcғXғYғүғ“ |

ғXғYғүғ“ӮМҺА
ҸHӮЙғIғҢғ“ғWҗFӮМҺАӮр•tӮҜӮЬӮ·ҒB |
|

үФғAғҚғG
ғuғӢғrғlҒ@ғtғӢғeғbғZғ“ғX |

ғIҒ[ғjғ\ғKғүғҖ |
ҢNҺq—–Ғi”ЮҠЭүФүИӮЙ•Ә—ЮӮіӮкӮйҺ–ӮаҒj |

ҺуӮҜҚзӮ«
Ғ@Ғ@Ғ@ҢNҺq—–
Ғ@‘ӯӮЙҢNҺq—–ӮЖҢҫӮҰӮОӮұӮМҺнӮЕӮ·ӮӘҒAҺАӮН–{–јӮНҒuҺуӮҜҚзӮ«ҢNҺq—–ҒvӮЖӮўӮӨҺн—ЮӮМҗA•ЁӮЕӮ·ҒB
Ғ@–{•ЁӮМҒuҢNҺq—–ҒvӮНҒAӮұӮкӮЖҺ—ӮҪӮжӮӨӮИҚЧӮў“ӣҸуӮМүәҗӮӮөӮҪӮВӮЪӮЭӮрӮВӮҜӮЬӮ·ӮӘҒAҗж’[•”•ӘӮӘӮнӮёӮ©ӮөӮ©ҠJӮ©ӮИӮўӮМӮЕҗlӢCӮӘӮИӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ·ҒB |
 ү©ӢаҠЫ ү©ӢаҠЫ
Ғ@Ғ~”Б“ьӮиҢn
Ғ@•iҺнүь—ЗӮМ“r’Ҷ’iҠKӮЕ•s—pӮЙӮИӮБӮҪҠ”Ӯр•ъҸoӮөӮҪ•ЁӮЕӮөӮеӮӨҒBӮЗӮсӮИүФӮӘҚзӮӯӮМӮ©ӮИҒHү©җFӮўүФӮҫӮЖ—ЗӮўӮИҒIӮЖҺvӮўӮИӮӘӮз”ғӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮQ”N—]ӮиҢoӮБӮҪҸHӮЙӢ¶ӮўҚзӮ«ҒBӢCү·ӮӘ’бӮӯӮДүФүиӮӘҗLӮОӮ№ӮёҒAӢ·Ӯў—tӮМҠФӮЙӢІӮЬӮБӮҪӮЬӮЬҺйҗFӮМүФӮНҚзӮҜӮёҺd•‘ӮЕӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөӢЖҺТӮНӮЗӮӨӮвӮБӮД–Ъ“IӮМҠ”ӮрҢ©•ӘӮҜҺжҺМ‘I‘рӮ·ӮйӮМӮ©ҒA•sҺvӢcҒI•sҺvӢcҒI |
Ғ@ү©ӢаҠЫҒ~”Б“ьӮиҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@2009”N5ҢҺ
Ғ@ҚрғVҒ[ғYғ“ӮНҸHӮЙғXғeғҖӮрҗLӮОӮіӮИӮўӮЬӮЬ—tӮБӮПӮМҠФӮЕүҹӮөӮВӮФӮіӮкӮй—lӮЙүФӮӘҚзӮ«ҺnӮЯӮДҸIӮнӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҢNҺq—–ӮМҗlҚHҢр”zҺнҒBӢGҗЯҠOӮкӮҫӮБӮҪӮ©ӮзҺd•ыӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮ©ӮИҒcӮЖҺvӮБӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAҚЎӢGӮН4ҢҺ––ӮЙӮИӮБӮДӮЬӮҪӮаӮв—tӮМҠФӮ©ӮзғIғҢғ“ғW“ьӮиӮМүФӮӘ1—ЦҚзӮўӮДӮўӮйҺpӮр”`Ӯ©Ӯ№ӮЬӮөӮҪҒBғXғeғҖӮрҗLӮОӮ·DNAӮӘҢҮӮҜӮДӮўӮйӮМӮ©ҒHҲзӮД•ыӮӘҲ«ӮўӮМӮ©ҒHӮЖҺсӮрҢXӮ°ӮДӮўӮҪӮЖӮұӮлҒAҸӯӮөӮёӮВҸӯӮөӮёӮВғXғeғҖӮрҗLӮОӮөҺnӮЯӮД2—Ц–ЪӮНүҪӮЖӮ©ҚӘҢіӮ©ӮзӮМ’EҸoӮЙҗ¬ҢчҒAӮ»ӮкӮЕӮа‘е•Ә”wӮН’бӮўҒBӮ»ӮөӮДҚXӮЙғXғҚҒ[ғeғ“ғ|ӮИӮӘӮзүФӮрҚзӮ©Ӯ№ӮИӮӘӮзғXғeғҖӮрҗLӮОӮөӮДҚsӮ«ҒAҚЕҢгӮМ8—Ц–ЪӮӘҚзӮӯҚ ӮЙӮН’КҸнӮМҗg’·ӮЙҒBӮөӮ©ӮөҒAҚзӮӯғeғ“ғ|ӮӘ’xүЯӮ¬ӮҪҲЧҒA‘S•”Ҳк“xӮЙҚзӮ«‘өӮӨҺ–ӮИӮӯ2—Ц–Ъ3—Ц–ЪӮМүФӮН—ҺӮҝӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒBҲкӮВҲкӮВӮМүФӮНүдӮӘүЖӮЙӮ ӮйҢГҠ”ӮМҢNҺq—–ӮжӮиӮаҸӯӮө‘еӮФӮиӮИӢCӮӘӮөӮЬӮ·ҒBӮ«ӮБӮЖ”Б“ьӮи—tӮЕү©җFӮўүФӮӘҚзӮӯҗV•iҺнӮрӢҒӮЯӮДӮўӮҪ“r’ҶӮМүЯ’цӮЙӮЁӮўӮДҺМӮДӮзӮкӮҪҠ”ӮЙҲбӮўӮИӮўӮЖҚlӮҰӮзӮкӮЬӮ·ӮӘҒAүҖҢ|үЖӮНҗVӮөӮӯҗ¶ӮЬӮкӮҪӮҪӮӯӮіӮсӮМҸ¬ӮіӮИ•cӮМӮӨӮҝӮ©ӮзҒAӮЗӮӨӮвӮБӮД–]ӮсӮЕӮўӮй—lӮИ”„Ӯи•ЁӮЙӮИӮйҠ”ӮрҢ©•ӘӮҜӮйӮМӮ©ҒH•sҺvӢcӮЕӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒBҠmӮ©ӮЙӮҝӮеӮБӮЖҸo—ҲӮ»ӮұӮИӮўӮМҠ”ӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ·ӮӘҒA—ҲғVҒ[ғYғ“ӮН“~ӮМҠЗ—қӮМҺd•ыӮр•ПӮҰӮДҒAҸtӮЙӮЬӮЖӮаӮЙүФӮӘҚзӮӯӮжӮӨӮЙӮөӮҪӮўӮаӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮөӮД–ј‘OӮа•tӮҜӮДҸгӮ°ӮЬӮөӮеӮӨҒBҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |

4ҢҺ–– |

5ҢҺ’ҶҸ{ |

5ҢҺ–– |

ӮbӮkӮhӮuӮhӮ` |
Ғ@ҢNҺq—–Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@2010”N3ҢҺ
Ғ©Ғ@үдӮӘүЖӮЙ—ҲӮДӮ©Ӯз3”N–ЪҒAӮжӮӨӮвӮӯүФӮрҚз
Ӯ©Ӯ№ӮДӮӯӮкӮЬӮөӮҪҒAү©үФӮЖҢҫӮӨӮжӮиӮағIғtғzғҸ
ғCғgҒA‘uӮвӮ©ӮЕҸг•iӮИүФҗFӮЕӮ·ҒB
Ғ@ҚЎ”NӮНӮҝӮбӮсӮЖүФүиӮрҗLӮОӮөӮДӮ©ӮзҒЁ
ҚзӮ«ӮЬӮөӮҪҒBүЯ•ЫҢмӮЙӮ№ӮёӮЙү®ҠOӮЕүz“~Ӯі
Ӯ№ӮҪӮҫӮҜӮИӮМӮЕӮ·ӮӘҒcҒBҗLӮСӮҪҢsӮрҢ©ӮҪӮзҒA
—ҘӢVҒi?ҒjӮЙӮа”Б“ьӮиӮЕғrғbғNғҠҒIүдүЖӮЙӮөӮБ
Ӯ©Ӯи’иҸZӮөӮДӮӯӮкӮДӮўӮйӮМӮЕҒA–ј‘OӮрjupiter
ӮЖ•tӮҜӮЬӮөӮҪҒBҺИ–Н—lӮ©ӮзҳA‘zӮөӮДӮМ–Ҫ–ј
ӮЕҒAҚЕҸүӮНzebraӮЙӮөӮжӮӨӮ©ӮЖҺvӮБӮҪӮМӮЕӮ·
ӮӘҒAӮіӮЩӮЗғnғbғLғҠӮөӮҪғXғgғүғCғvӮЕӮНӮИӮўӮМ
ӮЖҒAҚЕӢЯ–ШҗҜӮМҺИ–Н—lӮМҗ”ӮӘҢёӮБӮҪӮЖҢҫӮӨ
’ҝҢ»ҸЫӮрӢL”OӮөӮДҒAӮҝӮеӮБӮЖ—§”hӮ·Ӯ¬ӮйӮ©ӮИ
ӮҹҒcӮЖӮНҺvӮБӮҪӮаӮМӮМҒAҢҲ’иӮЕӮ·ҒIҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |

ӮiӮ•ӮҗӮүӮ”Ӯ…Ӯ’Ғiү©ӢаҠЫҒ~”Б“ьӮиҒ@үьӮЯҒj |
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@2012”NҸt
Ғ@ӮІӮӯ•Ғ’КӮМҢNҺq—–ӮМӮНӮёӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘ
ҒcҒBӮЖҢҫӮӨӮМӮаҒAҠ”•ӘӮҜӮөӮД‘қӮвӮөӮҪӮаӮМӮИ
ӮМӮЕҒAҗeҠ”ӮЖ“ҜӮ¶үФӮӘҚзӮўӮД“–‘RӮИӮМӮЕ
Ӯ·ӮӘҒA‘јӮМҠ”ӮМ•Ғ’КӮМүФӮӘҚзӮ«ҸIӮнӮБӮҪ
Қ ҒA’xӮкӮДү©җFӮўүФӮӘҢsӮрҗLӮОӮіӮёӮЙҚз
Ӯ«ӮЬӮөӮҪҒB“Л‘R•ПҲЩҒH•sҸҮӮИ“VҢуӮМӮ№
ӮўҒH•sҺvӢcӮИҸo—ҲҺ–ӮЕӮ·ҒB
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@ |
 |
ғAғKғpғ“ғTғXҒiҺҮҢNҺq—–Ғj
Ғ@ҚЎүсҚЪӮ№ӮйӮЙӮ ӮҪӮи’ІӮЧӮДӮЭӮДҒAҢNҺҮ—–ӮМ’ҮҠФӮЕҒA
ҺҮҢNҺq—–ӮЖҸүҢҫӮӨҳa–јӮрҺқӮВҺ–ӮаҸүӮЯӮД’mӮиӮЬӮөӮҪҒBӮЗ
ӮҝӮзӮа“мғAғtғҠғJӮӘҢҙҺY’nӮҫӮ»ӮӨӮЕҒAүФӮМҢ`ӮаҺ—ӮДӮўӮЬ
Ӯ·ӮөҒA”ЙҗB—НӮӘӢӯӮӯҲзӮДӮвӮ·ӮўӮЕӮ·ҒB
Ғ@ҹT“©ӮөӮў”~үJҺһӮЙҒA”–ҺҮӮМүФӮМҗFӮНҗҙ—БҠҙӮӘ—LӮБӮД
—ЗӮўӮЕӮ·ӮЛҒI |
 |
|

Ғ@ғxғSғjғA
ҒiғVғ…ғEғJғCғhғEүИҒj |
 |
 |
 |
 |
 |
Қч‘җүИӮМ’ҮҠФ
Ғ@ғvғҠғҖғүҒEғWғ…ғҠғAғ“
Ғ@“~Ӯ©ӮзҸtӮЬӮЕ’·ӮўҠФҠж’ЈӮБӮДүФӮр•tӮҜӮйғvғҠғҖғүӮНҒA”«җAӮҰӮЕүДӮрүzӮіӮ№ӮйӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮўӮВӮаҺcӮйӮМӮН’PҸғӮИүФӮрҚзӮ©Ӯ№ӮйҠ”ӮМӮЭҒB”ӘҸdҚзӮ«ӮҫӮБӮҪӮиҗFӮӘ•ЎҺGӮҫӮБӮҪӮиӮ·ӮйӮаӮМӮНҺгӮўӮжӮӨӮЕӮ·ҒBҒ@ |
Ғ@ғVғNғүғҒғ“
Ғ@’n’ҶҠCҢҙҺYӮЕҒCҢ»’nӮЕӮНӮ»ӮМӢ…ҚӘӮМҢ`Ӯ©ӮзҒu“ШӮМй\“ӘҒvӮЖӮўӮӨҲУ–ЎӮМ–іҗҲӮИ–ј‘OӮЕҢДӮОӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBҳa–јӮНүФӮСӮзӮӘҸгӮЙ”ҪӮи•ФӮйҺpӮӘвҫүОӮЙҺ—ӮДӮўӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒuвҫүОүФҒvӮЕӮ·ҒB
Ғ@ҸцӮөҸӢӮіӮЙҺгӮўӮМӮЕ‘е’пүДӮЙӢ…ҚӘӮӘ•…ӮБӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ӮӘҒAӮҪӮЬӮҪӮЬ–іҺ–ӮЙүДӮрүzӮөүдӮӘүЖӮЙ—ҲӮДӮQ”N–ЪӮЙӮаүФӮр•tӮҜӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©Ӯө‘fҗlӮМҠЗ—қӮЕӮН”«җAӮҰӮӘ“X“ӘӮрҸьӮйҺһҠъӮжӮиӮНӮйӮ©ӮЙ’xӮкӮДӮЩӮсӮМҸӯӮөӮҫӮҜҠJүФҒcӮИӮМӮЕҒAӮВӮўҗVӮөӮў”«ӮЙҺиӮӘҗLӮСӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒBӮӘҒAҲӨӮЁӮөӮіӮЕӮНҢГҠ”ӮМ•ыӮӘҸҹӮиӮЬӮ·ӮЛҒB |
 |

ғ~ғjғVғNғүғҒғ“ |
 ғKҒ[ғfғjғ“ғO—pғVғNғүғҒғ“ ғKҒ[ғfғjғ“ғO—pғVғNғүғҒғ“
Ғ@ӢЯ”N‘ПҠҰҗ«ӮМӢӯӮўғVғNғүғҒғ“ӮӘҸoүсӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBҺ„ӮН–Ҳ”NҸHӮЙ‘еӮ«ӮИғvғүғ“ғ^Ғ[Ҳк”tӮЙҗFӮЖӮиӮЗӮиӮЙҗAӮҰӮЬӮ·ҒBӮ»ӮөӮДүФҠъӮӘҸIӮнӮйҚ ӮМүФӮНҢӢҺАӮіӮ№ӮЬӮ·ҒBӮQ”NҲКҢoӮҝ‘еӮ«ӮИӢ…ҚӘӮЙҗ¬’·Ӯ·ӮйӮЖүФӮр•tӮҜӮй—lӮЙӮИӮиӮЬӮ·ӮӘҒA•Ғ’КӮМғVғNғүғҒғ““Ҝ—l‘fҗlҚН”|ӮЕӮНҸHӮ©ӮзүФӮрҲк”tӮВӮҜӮДӮНӮӯӮкӮЬӮ№ӮсҒBӮЕӮаӮұӮкӮӘ–{—ҲӮМҺpӮИӮМӮҫӮЖҺvӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB |
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@2009”N1ҢҺ
Ғ@җбҚчҒ@primurla sinensis
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@ҲкҚр”NӮМ”ғӮБӮҪҠ”ӮНүДӮӘүzӮ№ӮёӮЙҢНӮкӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAҚр”NҚw“ьӮөӮҪӮұӮМҠ”ӮНҸгҺиӮӯүДӮӘүzӮ№ӮДҒAҗV”N‘ҒҒXҚзӮ«ҺnӮЯӮЬӮөӮҪҒBҸцӮөҸӢӮіӮЙҺгӮӯӮДүДүzӮөӮӘ“пӮөӮўӮМӮЕҒA1”N‘җҲөӮўӮіӮкӮДӮўӮйҗA•ЁӮЕӮ·ҒBҺ„ӮНҸtӮЬӮЕҺҹҒXӮЖҚзӮӯ”’ӮўӮұӮМүФӮӘ‘еҚDӮ«ӮЕӮ·ҒBҚЎ”NӮМүДӮаҸгҺиӮӯүzӮ№ӮЬӮ·ӮжӮӨӮЙҒI |
 |
 |
|
|
|
ғCғҸғ^ғoғRүИӮМ’ҮҠФ |
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@2008”N10ҢҺ
Ғ@ғXғgғҢғvғgғJҒ[ғpғXҒ@ғTғNғ\ғӢғҖ
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@ӮЗӮӨӮағJғ^ғJғiӮМ–ј‘OӮНӢкҺиӮЕҒAҒuӮ ӮМ–ј‘O
ӮӘ“пӮөӮӯӮД’·ӮўҗA•ЁҒvӮЖҢҫӮӨӮМӮӘҒA•кӮЖ“сҗlӮЕ
ӮұӮМҗA•ЁӮЙ•tӮҜӮҪ–ј‘OӮЕӮ·ҒB
Ғ@ҢsӮрҗШӮБӮДҗ…ӮЙҚ·ӮөӮДӮЁӮҜӮОҒAҗЯӮ©ӮзҚӘӮӘҸo
ӮДӮЗӮсӮЗӮс‘қӮҰӮЬӮ·ҒBүдӮӘүЖӮМӮұӮМҠ”ӮаҺАүЖ
ӮМҺqҠ”ӮЕӮ·ҒB2.5ӮғӮҚҲКӮМ–К’·ӮМүФӮрҸHӮ©ӮзҸү
“~ӮЙӮ©ӮҜӮДҺҹҒXҚзӮ©Ӯ№ҒAҺиӮӘҠ|Ӯ©ӮзӮИӮў—D“ҷ
җ¶ӮЕӮ·ҒBҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |
 |
|
|
 |
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@2009”N11ҢҺ
Ғ@ғXғgғҢғvғgғJҒ[ғpғXҒEғNғҠғXғ^ғӢғAғCғX
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@ғXғgғҢғvғgғJҒ[ғpғXӮН—LҢsҺнӮЖ–іҢsҺнӮӘӮ ӮиҒAӮұӮМғN
ғҠғXғ^ғӢғAғCғXӮН–іҢsҺнӮЕӮ·ҒBҸtҒEҸHӮМ1”NӮЙ2үсүФӮр
ҚзӮ©Ӯ№ӮЬӮ·ҒBғTғNғ\ғӢғҖӮЖ“Ҝ—lҒAҺиӮӘҠ|Ӯ©ӮзӮёҺҹҒXӮЙ
үФӮрҲк”tҚзӮ©Ӯ№Ӯй—D“ҷҗ¶ӮМҗA•ЁӮЕӮ·ҒB
Ғ@җМӮНҢ©Ҡ|ӮҜӮИӮ©ӮБӮҪғXғgғҢғvғgғJҒ[ғpғXӮЕӮ·ӮӘҒAҚЕӢЯ
“X“ӘӮЙ•АӮФҺн—ЮӮӘ‘қӮҰӮДӮўӮй—lӮИӢCӮӘӮөӮЬӮ·ҒBҺиҢy
ӮЙҚН”|Ҹo—ҲӮйӮ©ӮзӮ©Ӯа’mӮкӮЬӮ№ӮсӮЛҒB |
|
|
 |
Ғ@ғXғgғҢғvғgғJҒ[ғpғXҒEғTғNғ\ғӢғҖӮrҒ@ҒiғCғҸғ^ғoғRүИҒj
Ғ@6ҢҺӮЙҚзӮўӮҪҲк”ФүФӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМҢгүФүиӮӘғhғ“ғhғ“ҸгӮӘӮБӮД—ҲӮД
ҺҹҒXӮЙҚзӮўӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAғTғNғ\ғӢғҖӮН—LҢsҺнӮЙ•tӮўӮДӮўӮй
–јӮИӮМӮЙҒAӮrӮӘ•tӮўӮДӮўӮйӮЖӮНҢҫӮҰҒAғҚғ[ғbғgғ^ғCғvӮМӮұӮкӮЙ•tӮў
ӮДӮўӮйӮМӮНҒAӮаӮөӮ©ӮөӮДҺDӮӘҲбӮӨӮ©ӮаҒHӮЖӢ^–вӮЙҺvӮўӮЬӮ·ҒB
Ғ@ғXғgғҢғvғgғJҒ[ғpғXӮЖӮНҒAҒuӮЛӮ¶ӮкӮҪүКҺАҒvӮЖӮўӮӨҲУ–ЎӮЕҒAүКҺАӮӘ
ҸnӮ·ӮЖӮЛӮ¶ӮкӮДғ^ғlӮрӮЖӮОӮ·ӮұӮЖӮ©ӮзҒAӮұӮМ–ј‘OӮӘ•tӮўӮҪӮ»ӮӨӮЕ
Ӯ·ҒBӮөӮ©Ӯө‘јӮМ2Һн—ЮӮМғXғgғҢғvғgғJҒ[ғpғXӮЙҺАӮӘ•tӮўӮДӮўӮйӮМӮр
Ң©ӮҪҺ–ӮӘӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮМӮЕҒAҲк“xҺАӮрҢ©ӮДӮЭӮҪӮўӮИӮҹҒcӮЖҺvӮБӮДӮў
ӮЬӮ·ҒB
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |
|
Ғ@ғLғNүИӮМ’ҮҠФ
Ғ@ғSҒ[ғӢғfғ“ҒEғsғүғ~ғbғh
Ғ@
Ғ@2009”NӮМүФӮЙ”дӮЧӮДҒA2010”NӮНүФӮСӮз
ӮӘ‘ҫӮӯ’ZӮўүФӮӘҚзӮ«ӮЬӮөӮҪҒB”ЙҗB—Нү җ·
ӮЕҒAүФӮӘҚзӮ«ҺnӮЯӮйҚ ӮЙӮНҒAҠщӮЙүәӮЙӮНҗV
үиӮӘҠзӮрҸoӮөӮДӮўӮйӮЖҢҫӮӨҸуӢөӮЕӮ·ҒB |
|
 |
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@2009”N11ҢҺ
Ғ@ғEғBғ“ғ^Ғ[ҒEғRғXғӮғXҒ@
Ғ@Ғ@•К–јҒGғLғNғUғLғZғ“ғ_ғ“ғOғTҒiӢeҚзӮ«җс’h‘җҒjҒAғrғfғ“ғX
Ғ@“ҜӮ¶ғLғNүИӮМғRғXғӮғXӮЖӮНҲбӮӨ‘®ӮМҗA•ЁӮЕӮ·ӮӘҒAүФӮМҚзӮўӮДӮўӮйҺpӮӘҺ—ӮДӮўӮйӮМӮЕҒA
ғEғCғ“ғ^Ғ[ҒEғRғXғӮғXӮЖҢҫӮӨ–ј‘OӮӘӮВӮҜӮзӮкӮҪӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒB
Ғ@ӮЬӮҫҸӢӮўӮӨӮҝӮЙ”ӯүиҒAғhғ“ғhғ“ғhғ“ғhғ“җLӮСӮДҒAӮўӮВӮЗӮұӮЙүФӮӘҚзӮӯӮМҒHӮЖҺvӮБӮДӮўӮйӮӨӮҝ
ӮЙҢsӮНӮQӮҚҲКӮЙҒBӮ»ӮМ“r’ҶӮ©ӮзӮаҢsӮЖҚӘӮӘҸoӮДӮЬӮҪҗLӮСӮйҒAӮЖҢҫӮБӮҪӢпҚҮӮЕҒAӮ©ӮИӮиҗ¶
–Ҫ—НӮӘӮҪӮӯӮЬӮөӮўҠҙӮ¶ӮӘӮөӮЬӮ·ҒBӮ»ӮөӮДӮжӮӨӮвӮӯүФӮӘҚзӮўӮҪӮМӮӘ11ҢҺӮЙ“ьӮБӮДӮ©ӮзӮЕӮө
ӮҪҒBҚXӮЙҠ”ҢіӮ©ӮзӮНӮЬӮҫӮЬӮҫӮҪӮӯӮіӮсүиӮӘҸoӮД—ҲӮДӮўӮйӮМӮЕҒAүФӮМҢ`Ӯрҗ®ӮҰӮйҲЧӮЙӮНҒA
ҚЕҸүӮМҢsӮНҗLӮОӮіӮёҗШӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪ•ыӮӘ—ЗӮўӮМӮ©ӮаҒHӮЖҒA—ҲғVҒ[ғYғ“ӮЙҢьӮҜӮДӮМ”ҪҸИ
ӮЕӮ·ҒB |

ғTғ}Ғ[ғ\ғ“ғOғfғBҒ[ғvғҚҒ[ғY |

ғ{Ғ[ғ_Ғ[ғzғҸғCғg |
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@2013”N4ҢҺ
Ғ@ғ}Ғ[ғKғҢғbғgҒ@
Ғ@ҚрҸt”ғӮБӮҪғ}Ғ[ғKғҢғbғg2Һн—ЮҒB
ғTғ}Ғ[ғ\ғ“ғOғfғBҒ[ғvғҚҒ[ғYӮНҒA’јҢa1Үp
ҲКӮМүФӮӘҺҹҒXӮЙҚзӮ«ҒAғsғ“ғNӮМҸ¬ҺRӮӘӮұ
ӮсӮаӮиҸo—ҲӮДҒAҢ©Һ–ӮЕӮ·ҒBҚзӮ«ҸIӮнӮБӮҪүФ
•ҝӮр“EӮЮӮМӮӘҲкҺdҺ–ӮЕӮ·ҒB
ғ{Ғ[ғ_Ғ[ғzғҸғCғgӮМ•ыӮНҒAӮ»ӮкӮжӮиӮН‘еӮ«
Ӯў’јҢa4Ғ`5ҮpӮМүФӮӘҚзӮ«ӮЬӮөӮҪӮӘҒA3—Ц
ӮҫӮҜҒBҗQӮ»ӮЧӮБӮҪҠҙӮ¶ӮИӮМӮНҒAҲзӮД•ыӮӘ
Ҳ«Ӯ©ӮБӮҪӮМӮ©ҒHғ{Ғ[ғ_Ғ[ӮМ–јӮМ”@ӮӯҒAүФ
’dӮМүҸҺжӮи—pӮЙӮ·ӮЧӮ«ӮИӮМӮ©ҒHӮжӮӯ•ӘӮ©
ӮиӮЬӮ№ӮсӮӘҒAҚH•vүь—ЗӮМ—]’nӮ ӮиӮЕӮ·ҒBҒ@
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |

ғCғGғҚҒ[ғ`ғғҒ[ғҖ |
Ғ@ғrғfғ“ғXҒ@
Ғ@ү©җFӮўүФӮӘ—~ӮөӮӯӮДҒAҚрҸH”ғӮБӮҪғrғfғ“ғXӮЕӮ·ҒBҸtӮЖҸHҒA1”NӮЙ2үсҚзӮ«ӮЬӮ·ҒB”«ӮМ“yӮӘҢ©ӮҰӮИӮӯӮИӮйӮЩӮЗ—tӮӘ–ОӮБӮДӮӯӮкӮйӮЖ—ЗӮўӮМӮЕӮ·ӮӘҒAҚЧӮ©ӮўӮМӮЕ“пӮөӮўӮМӮ©Ӯа’mӮкӮЬӮ№ӮсҒB
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |
|
|
Ғ@ғTғ{ғeғ“үИӮМ’ҮҠФ |
 |
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@2009”N12ҢҺ
Ғ@ғfғ“ғ}Ғ[ғNҒEғJғNғ^ғXҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@ӮұӮМғTғ{ғeғ“ӮНҒAүдӮӘүЖӮЕӮНҢГҠ”ӮИӮМӮЕӮ·ӮӘҒA–wӮЗ
үФӮр•tӮҜӮйҺ–ӮӘ–іӮ©ӮБӮҪӮМӮЕҒA’лӮМӢчӮЙ’ЗӮўӮвӮзӮк
ӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮӘҒAҗV“ьӮМғXҒ[ғpҒ[ҒEғPғjғKҒ[ӮӘҚр“~ӮҪӮӯ
ӮіӮсӮМүФӮрҚзӮ©Ӯ№ӮҪӮМӮЕ”ӯ•ұӮөӮҪӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒHӮ»Ӯк
ӮЖӮағnғ“ғMғ“ғOҒEғoғXғPғbғgӮ©ӮзҗAӮҰ‘ЦӮҰӮҪӮМӮӘҢшӮр‘t
ӮөӮҪӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒHҢ©Һ–ӮЙүФӮрҚзӮ©Ӯ№ӮДӮӯӮкӮЬӮөӮҪҒB
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |
|
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@2008”N12ҢҺ
Ғ@ғXҒ[ғpҒ[ҒEғPғjғKҒ[
ғfғ“ғ}Ғ[ғNҒEғJғNғ^ғX
Ғ@үдӮӘүЖӮЙ—ҲӮДӮ©ӮзүҪ”NҢoӮВӮМӮЕӮөӮеӮӨҒH“ъ
“–ӮҪӮиӮӘҲ«Ӯў’лӮИӮМӮЕӮЬӮёүФӮӘҚзӮӯҺ–ӮНӮИ
ӮўӮҫӮлӮӨӮЖ’ъӮзӮЯӮД–ЪӮрҠ|ӮҜӮйҺ–ӮаӮИӮӯ•ъӮБӮД
ӮЁӮўӮҪӮМӮЙҒAеQӮӘӮҪӮӯӮіӮсҒIӮҪӮӯӮіӮсҒIӮВӮў
ӮДӮўӮйӮМӮрӮЭӮВӮҜӮҪҺһӮНҠҙҢғӮЕӮөӮҪҒBӮұӮсӮИ
ӮЙҲк“xӮЙүФӮӘҚзӮӯӮЖҢ©Һ–ӮЕӮ·ҒBҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |
 |
 |
 |
Ғ@ғEғ`ғҸғTғ{ғeғ“Ғ@ҒiғTғ{ғeғ“үИҒj
Ғ@ҚрҸHғEғ`ғҸғTғ{ғeғ“ӮМҢsӮр–бӮБӮД—ҲӮД“y
ӮМҸгӮЙҗQӮ©Ӯ№ӮДӮЁӮ«ӮЬӮөӮҪҒBҸtӮЙӮИӮБӮДӮж
ӮӨӮвӮӯүиӮрҸoӮөҒAbabyӮНҸ¬ӮіӮўӮИӮӘӮзӮаӮҝӮб
ӮсӮЖӮ»ӮкӮИӮиӮМҢ`ӮрӮөӮДӮўӮйӮМӮӘҒAӮИӮсӮЖӮа
үВҲӨӮўӮЕӮ·ҒB‘ҒӮӯ‘еӮ«ӮӯӮИҒ`ӮҹӮкҒI
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |
|
Ғ@ғxғ“ғPғCғ\ғEүИӮМ’ҮҠФҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@”’‘MҠҘҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ҹг’i’Ҷүӣ
Ғ@•sҺҖ’№Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ҹг’iүE
Ғ@”–җб•ЩҢc‘җҒ@Ғ@үә’i’Ҷүӣ
Ғ@•ЩҢc‘җҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@үә’iүE
Ғ@—tӮӘҢъӮӯҒCҗШӮиҺжӮБӮДҺbӮӯӮЁӮўӮДӮаӮөӮЁӮк
ӮёҒC“yӮЙ‘}Ӯ·ӮЖҚӘӮӘҸoӮДҢіӢCӮжӮӯҲзӮҝӮНӮ¶
ӮЯӮйҒAӮЬӮҪҸӢӮіҠҰӮіӮЙӢӯӮўҒAӮұӮМ—lӮИҸд•v
ӮИҗ«ҺҝӮр•ЩҢcӮЙ—бӮҰӮДғxғ“ғPғCғ\ғEӮЖ–ј•t
ӮҜӮзӮкӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮМӮжӮӨӮИҗ«
ҺҝӮНҒCғxғ“ғPғCғ\ғEүИӮМҗA•ЁӮЙӢӨ’КӮ·Ӯй
“Б’ҘӮЕӮаӮ ӮиҒA“ҜӮ¶ҲУ–ЎҚҮӮўӮЕғCғLғNғT
ҒiҠҲ‘җҒjӮЖӮўӮӨ•К–јӮаӮВӮҜӮзӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB
Ғ@Ҹг’iӮМ2”«ӮНҗV“ьӮиӮИӮМӮЕүФӮӘҚзӮӯӮМ
Ӯ©ӮЗӮӨӮ©ӮН•ӘӮ©ӮиӮЬӮ№ӮсҒBҒu”’‘MҠҘҒvӮЖҢҫӮӨ
ӮМӮНҢМҺ–ӮЙ—R—ҲӮ·ӮйӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒAүҪӮвӮз
—§”hӮИ–ј‘OӮЕӮ·ҒB
Ғ@”–җб•ЩҢc‘җӮН5ҢҺӮЙӮ ӮЬӮи–Ъ—§ӮҪӮИӮў
ү©җFӮўүФӮр•tӮҜӮЬӮ·ҒB“~ӮЙӮН‘O”NӮМҢsӮМ
ҢіӮЙ”’ӮБӮЫӮўҗVүиӮӘӮҪӮӯӮіӮсҸoӮД—ҲӮЬӮ·ҒB
”–ӮӯҗбӮӘҗПӮаӮБӮҪӮжӮӨӮЙҢ©ӮҰҒAӮұӮкӮӘ–ј‘O
ӮМ—R—ҲӮ©ӮаҒcҒBӮ»ӮөӮДүДӮН”–—ОҗFӮМҚЧӮў
—tӮӘ”’ӮӯүҸҺжӮзӮкӮДӮўӮД—БӮөӮ°ӮЕӮ·ҒBүФӮр
ҲӨӮЕӮйҗA•ЁӮЖҢҫӮӨӮжӮиӮаҠП—tҗA•ЁӮМ—lӮИ
ҠҙӮ¶ӮЕӮ·ҒB
Ғ@•ЩҢc‘җӮН10ҢҺӮЙғsғ“ғNӮМүФӮрҚзӮ©Ӯ№ӮЬ
Ӯ·ҒBҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |
 |
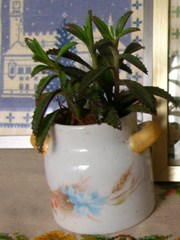 |
 |
 |
 |
Ғ@•sҺҖ’№
Ғ@Қр”NӮН5ҢҺӮЙ—tӮМүҸӮЙүҲӮБӮДүҪӮвӮзғqғүғqғүӮөӮҪ•ЁӮӘҲк”t•tӮўӮДӮўӮйӮМӮЙӢC•tӮ«ҒAӮаӮөӮ©ӮөӮҪӮзүФҒHӮЖӢCӮЙӮНӮөӮИӮӘӮзӮа1ӮҚӮҚҲКӮөӮ©ӮИӮўҚЧӮ©Ӯў•ЁӮИӮМӮЕӮ»ӮМӮЬӮЬ•ъ’uӮөӮҪӮзҒAӮ»ӮМҢг—ЧӮМ”«Ӯ©ӮзҢsӮӘү„ӮСӮД—ҲӮЬӮөӮҪҒBӮвӮБӮПӮиүФӮӘҚзӮўӮДӮўӮҪӮМҒHҚЎ”NӮұӮ»—ЗӮӯҠПӮжӮӨҒIӮЖ ҺКҗ^ӮрҺBӮБӮҪҸҠҒA•sҺvӢcӮИ•ЁӮӘҒcҒB’ІӮЧӮҪҸҠҒu—tӮМүҸӮЙ•s’иүиӮрӮВӮҜҒAӢCҚӘӮрҗӮӮзӮөҒA•Ә—ЈӮөӮД‘қҗBӮ·ӮйҒBҒvӮЖӮМҺ–ҒAүФӮЕӮНӮИӮӯҺqүиӮЕӮөӮҪҒBҠИ’PӮЙҗBӮвӮ№ӮйӮ»ӮӨӮИӮМӮЕҒAӮаӮӨҸӯӮөӮөӮҪӮзҺqүиӮр“yӮМҸгӮЙ’uӮўӮДӮЭӮжӮӨӮ©ӮЖҺvӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBҒA |
Ғ@Ҹј—tӮВӮГӮиҒ@
Ғ@ҚрҸHҒAӢЯҸҠӮЕҺR–м‘җӮЖӮөӮД”„ӮзӮкӮДӮўӮҪ
”«ӮрҚw“ьӮөӮЬӮөӮҪҒB—tӮМҗFӮӘӮЖӮДӮагY—нӮЙ
ҠҙӮ¶ҒAӮұӮкӮ©ӮзҢ}ӮҰӮй“~ӮМҺһҠъӮЙӮНӢMҸdӮИ
—ОҗFҒIӮЖҺvӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒBӮөӮ©Ӯа‘ПҠҰҗ«ӮӘ
ӢӯӮўӮ»ӮӨӮЕҒAү®ҠOӮЕӮа•ҪӢCҒI
Ғ@6ҢҺӮЙӮИӮиҒA—tӮМҗжӮЙҲк”tү©җFӮўүФӮрҚз
Ӯ©Ӯ№ӮЬӮөӮҪҒB”–җб•ЩҢc‘җӮМүФӮЖ—ЗӮӯҺ—ӮДӮў
ӮЬӮ·ӮӘҒAӮұӮҝӮзӮМ•ыӮӘ‘¶ҚЭҠҙӮӘӮ ӮиӮЬӮ·
ӮЛҒB
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |
 |
 |
 |
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@2009”N4ҢҺ
Ғ@ғJғүғ“ғRғGҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@Ҳк”ФүФӮӘ2ҢҺҸүӮЯӮЙҚзӮ«ҺnӮЯӮДӮ©Ӯз2ғJ
ҢҺӮ©Ӯ©ӮБӮДҒAӮдӮБӮӯӮиӮдӮБӮӯӮиҚз‘өӮўӮЬӮө
ӮҪҒBҺАӮНӮұӮМ”«ҒAүДӮЙү©җFӮўүФӮӘҚзӮўӮД
ӮўӮҪӮМӮрҒA‘e•iӮЕ–бӮБӮҪӮаӮМӮЕӮ·ҒB’Z“ъҗA
•ЁӮЕҺ©‘RӮЙӮЁӮўӮДӮЁӮҜӮО“~ӮЙҠJүФӮЖӮН’m
ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪӮөҒAӮЬӮөӮДғsғ“ғNӮМүФӮӘҚзӮӯ
ӮЖӮНҒIӮөӮ©Ӯө’iҒXүФҗFӮӘү©җFӮЙ•Пү»ӮөӮД
ӮўӮӯӮЭӮҪӮўӮЕӮ·ҒBеKеNӮЖ“ҜӮ¶ӮӯӢGҗЯӮӘҲбӮӨ
ӮЖүФ•ЩӮМҗFӮӘ•ПӮнӮйӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒHӮ»ӮөӮД
ғxғ“ғPғCғ\ғEүИӮМ’ҮҠФӮИӮМӮЙҒAҸӢӮіҠҰӮіӮЗ
ӮҝӮзӮЙӮа‘Пҗ«ӮӘ’бӮў—lӮЕҒAҢ©Ӯ©ӮҜӮжӮиӮаӮР
ҺгӮЕӮ·ҒBҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |
|
| Ӯ»ӮМ‘јӮМ’ҮҠФ |
|
|
 |
Ғ©ҸҢ•—ҳIҒiғtғEғҚғ\ғEүИҒj
Ғ@ғAғPғ{ғmғtғEғҚҒiғ[ғүғjғEғҖҒEғTғ“ғOғCғl
ғEғҖҒjӮНҒC“ъ–{ӮМ–м‘җӮМӮжӮӨӮИ–јӮрӮөӮДӮў
ӮЬӮ·ӮӘҒAүўҸBҒ`җјғAғWғAӮМҚӮ’nӮЙҗ¶ҲзӮ·
ӮйҠO—ҲҺнӮЕӮ·ҒB–…ӮӘҗ…ҸгӮ©Ӯз”ғӮБӮД—ҲӮҪ
ӮМӮрҸчӮиҺуӮҜӮЬӮөӮҪҒB4ҢҺӮ©ӮзҺҹҒXӮЙҸ_Ӯз
Ӯ©ӮўүФӮСӮзӮМүВ—чӮИүФӮрҚзӮ©Ӯ№ӮЬӮ·ӮӘҒA1
“ъӮЕҺUӮБӮДӮөӮЬӮӨӮӘҷRӮўҠҙӮ¶ӮЕӮ·ҒB
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ғ~ғҠғIғ“ғxғӢҒiғiғXүИҒjҒЁ
Ғ@1”N‘җӮЖӮөӮД”„ӮБӮДӮўӮЬӮ·ӮӘҒAҢsӮаҢНӮк
ӮёӮЙҺcӮБӮДӮўӮҪӮМӮЕ‘К–ЪҢіӮЕүz“~ӮіӮ№ӮҪ
ӮЖӮұӮлҒA4ҢҺӮЙӮИӮБӮДүФӮӘҚзӮ«ҺnӮЯӮЬӮөӮҪҒB
ғ~ғҠғIғ“ғxғӢӮЖҢҫӮӨ–јӮМ”@ӮӯҒAҺҹҒXӮЙүФӮӘ
•tӮ«ӮЬӮ·ҒBҢsҢіӮН–ШӮМ—lӮИ”§ӮрӮөӮДӮўӮДҒA
ҺАӮН’б–ШӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮкӮр1
”N‘җӮЖӮөӮД”„ӮБӮДӮўӮйӮМӮНҸӨҚ°з—ӮөӮў—l
ӮИӢCӮӘӮөӮЬӮ·ҒB |
 |
|